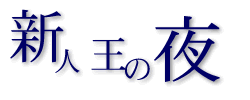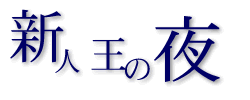|
全日本新人王戦・沖田佳吾優勝。
その夜の仲代ジムの打ち上げ。
「誰だ。沖田に酒飲ませた奴は!」
「伊達さん、そいつ乾杯のときしか飲んでませんよー」
「…なら何でもうこんなに酔ってるんだよ」
まだ会が始まって間もないのに、沖田は酔っていた。
元々酒は強くない。しかもさっきまで全力で打ち合いをしていたのだ。
酒の回りがよすぎても仕方のないことであった。
顔を赤らめ、すでに目の焦点が泳いでいる。ロレツも回っていなかった。
「お前な、試合の後あまり飲むとヤバイんだぞ。おい聞いてるのか、沖田」
他の者達はすでに沖田の優勝にかこつけて騒ぎたい放題だった。
しかし、伊達は今日の本来の主役である、この男の相手をマメにしていた。
伊達の忠告を聞いているのかいないのか、気持ちよさげに空を見るだけであった。
「…ったく、しょうがねーな。ま、今日はお前が主役なんだからいいけどな」
伊達が一度引退して再びリングに戻ってきた。沖田はその再起戦をTVで見ていた。
身震いするような感覚。 今まで感じたことのない衝撃。
その日から、沖田にとって伊達は「一生の人」となった。
どうしても伊達の近くでボクシングをしたくて、同じジムに入り、そして−。
「いいスジしてるぜ、お前」
「…そ、そうですか!?」
もっと近くで技を見たい、盗みたい…。もっとこの人のように強くなりたい…。
そう思ってずっとやっていたことが報われる瞬間だった。
この人がいる限り、俺はここから抜け出せない−−
そう思っていた。
あっという間にデビュー戦が決まり、トントン拍子に新人王トーナメントも
勝ち続けていった。
もっともっと早くあの人の近くへ…
沖田は自分の気持ちに微妙な変化が起こったことを気づき始めていた。
「憧れ」や「尊敬」があまりに近くにいつづけること、優しくされることによって、
「ボクサー」として、だけではなく、「一人の男」として伊達を想っていることに。
妻子もいて、日本ボクサー界のトップに立つ男。
わかっていた、どうにもならないことは。しかし、自分の気持ちを抑えられないことも
同じくどうにもならないことであった。
彼はまだ若かった。
その若さがよくも悪くも伊達を迷わすことはまだ先のことではあったが。
主役をないがしろで大いに盛り上がった打ち上げも無事解散となった。
乾杯のビールをコップ半分で信じられないくらい泥酔している沖田は、トレーナーや
会長の命令もあって伊達が家まで送ってやることになった。
「お前になついているんだから、お前が責任とって送ってやれよ」
沖田はジムの近くのハイツに一人暮らしをしていた。
1年以上近くにいるが、伊達は沖田の家に上がるのは始めてだった。
「うぉーい、沖田着いたぞー。お前のうちだぞ。ホラ起きろ」
引きずるように部屋に連れていき、電気をつける。
「げ!俺のポスターなんざはってやがる…」
何ともいえない気持ちになって、肩を貸している沖田の顔をのぞき込む。
「…グラビアアイドルの気持ちってこーいう感じなんだろーなぁ…。
でもやっぱり身内だとくすぐってぇや…」
照れつつも悪い気はしない。
沖田が自分を慕っていることは決して嫌なことではなかった。
他の奴らにはプライドの高さをあからさまに出し、高圧的な態度をとるような
沖田が、自分の前だけ素直でいることは伊達も気づいていたことだ。
そして、その視線が「尊敬」などというものから越えつつあることも…。
しかし、伊達は「大人」だった。
好かれる者は無下にはしない。だからといって、自分から何か態度に出したりは
絶対にしなかった。
若い頃さんざん遊んだからこそ、出来ることである。
彼も、家庭を、妻を子を、愛しているのだ。
しかし…。
「オラ!もう寝ろよ。俺はもう帰るからな!」
「う〜ん…」
「ちゃんと着替えろよ!おい!起きてんのか?」
「…伊達さん…」
「……何だ」
「俺、勝ちましたよ。新人王ですよ…」
「ああ。お前はすげえ。俺が思ってたより全然強えぞ。正直ビックリしたよ」
「…すぐに…行きますから」
「ん?何だ?」
もうすでに寝ていた。
伊達はその寝顔を見ながら、笑った。
「しょーがねーなー、これはごほうびだ。っつってもきっと起きたらお前は
覚えてないだろうけどな」
沖田の寝顔に顔を重ねた。
勿論、沖田はこのことは覚えていない。
|